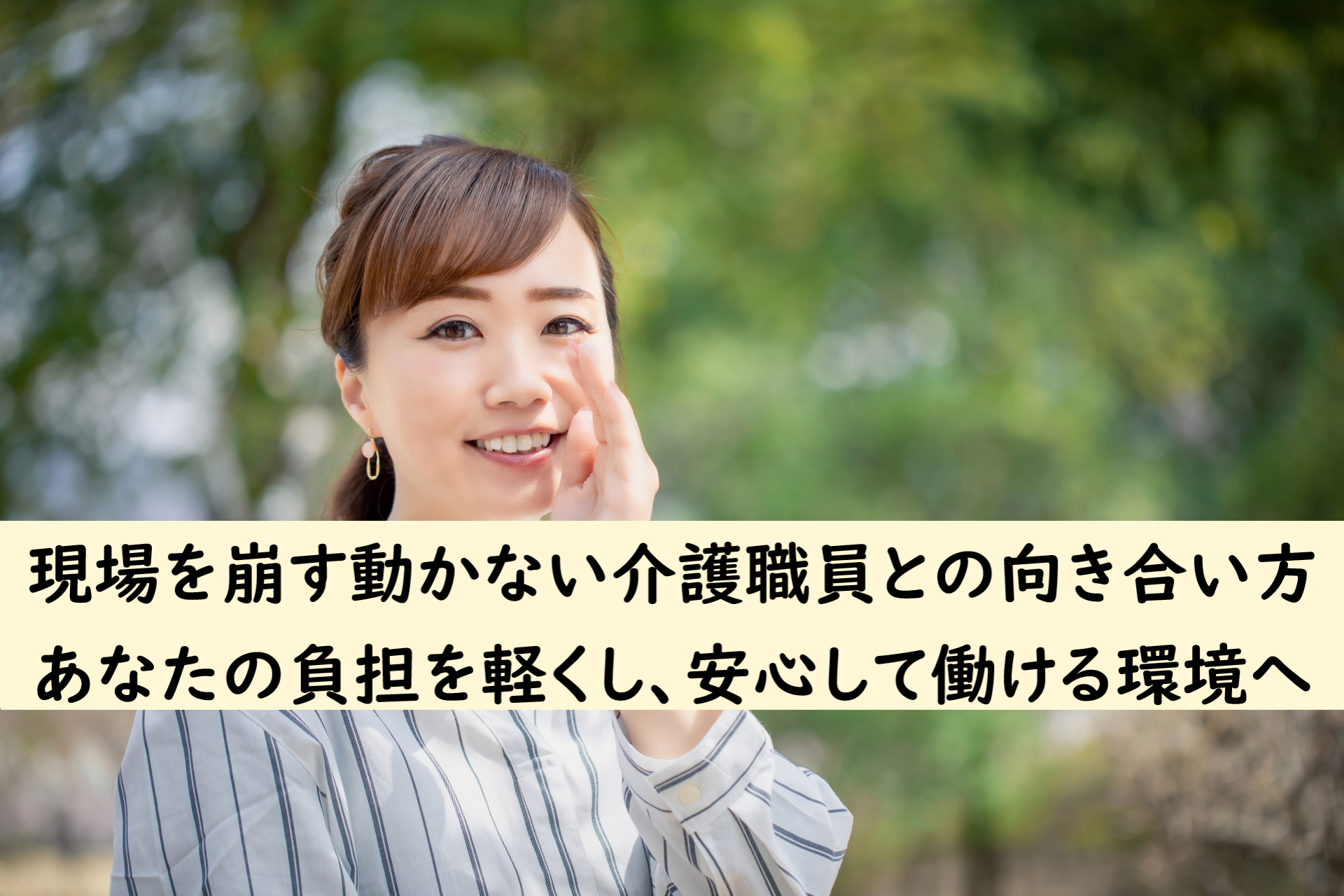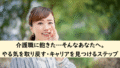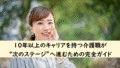「介護転職パーク」は、株式会社マイナビ・株式会社エス・エム・エス・株式会社ミラクス・レバレジーズ株式会社・パソナグループ・株式会社ニッソーネット・株式会社ウィルオブ・ワーク等の複数企業とアフィリエイトプログラム提携し、情報提供を行っております。当サイトを経由して商品への申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために還元しております。
介護の現場で働いているあなたなら、こんな瞬間を経験したことがあるかもしれません。
「自分だけ忙しくて、あの人はあまり動いていないのに給料が同じかほぼ同じ」
「せっかくチームで動らなきゃいけないのに、あの人が動いてくれないから業務が滞る」
「利用者さんへのケアの質が落ちているかもしれないと感じる」
このような「動かない職員」「責任感が乏しい職員」「いわゆる“モンスター職員”」と呼ばれてしまう職員がひとりでもいると、職場全体の雰囲気も、あなた自身のモチベーションも、そして利用者さんへのサービスの質も、ゆがんでしまう可能性があります。
この記事では、そうした職員が「なぜ動かないのか」「どんな特徴があるのか」「あなたはどう関わるべきか」、そして「そのまま働き続けていいのか/転職を考えるべきか」という選択肢まで、具体的に解説します。
読後には「自分は今、どこに立っているのか」を整理でき、「次に向かうための一歩」が明確になります。
経験豊富なプロが執筆!安心の情報源
この記事は、転職成功者500人以上、相談者2000人以上をサポートしてきた現役の介護職転職エージェントが、実際の経験や体験談をもとに執筆しています。
転職を成功させるための ノウハウや具体的なテクニック をたっぷりお届けしますので、ぜひ最後までお読みください!
介護・福祉の求人を厳選!!「リニューケア」

1.関西圏に特化した地域密着型の求人サイト✨
2.業界5年以上のコンサルタントが在籍!!
3.地域密着型だからこその非公開求人が充実!!✨ 4.履歴書添削・面接同行も完全無料の徹底サポート!!
リニューケアは介護福祉に特化した求人サイトです!
業界5年以上のコンサルタントが在籍しており、安心してご利用頂けます。
求人サイトや転職エージェントは複数登録が一般的なので、リニューケアにも登録して転職の幅を広げましょう!!
\無料登録は下記公式サイトから/
動かない介護職員とは―その定義と影響
まず、「動かない職員」「モンスター職員」という言葉を使っていますが、ここでは次のような状態を指します。
- チームワークを乱すような言動がある(協調性の欠如)
- 自分の仕事に責任を持たず、放置・軽視する
- 向上心がなく、積極的に新しいことを学ぼうとしない・苦手なことを避ける
- 休憩が多かったり、業務中に私的なことを優先したりする
- ミスを繰り返すのに改善しなかったり、言い訳や他責の発言がある
このような職員が介護現場にいると、以下のような悪影響が生じます。
- あなたを含め、動いている職員の負担が増える
- チームとしての機能が低下し、サービス提供がスムーズに行えない
- 利用者さんが「この人に頼んで大丈夫かな」と不安を感じる可能性がある
- 職場の雰囲気が悪化し、士気が下がる、離職につながることもある
実際、介護現場において「仕事をしない人がいると職場の雰囲気が悪くなり、他の職員の離職に繋がる」という指摘もあります。
また、人間関係の不調は離職理由の上位にあるという統計も出ています。
このように「動かない職員」は“理解できない個人の怠慢”としてだけ捉えるのではなく、職場の構造・環境・あなた自身が感じる重荷として捉えておくことが重要です。
動かない介護職員の特徴を深掘り
ここではもう少し具体的に、「動かない/モンスター職員」と言われる人が持ちやすい特徴を整理します。
あなたが「この人、あてはまるな」と感じる職員がいるなら、以下のチェックリストとして使えます。
協調性・責任感の欠如
- チームミーティングや申し送りに参加しても発言がない、消極的。
- 自分の仕事の範囲外だと「それは私の仕事じゃない」と明言する。
- 関係者(同僚・利用者・家族)への配慮が足りず、「自分さえ良ければいい」「自分のペースで」の雰囲気。
このような態度は、チームワークが前提となる介護現場にあって重大なズレを生みます。
責任の所在があいまいになると、「誰がやるのか」「いつやるのか」が不明確になりがちです。
向上心・積極性の欠如
- 新しい介護手法や介護ロボット・ICT導入などに「そんなの必要ない」「今のままでいい」と興味を示さない。
- 苦手な業務・それまで自分があまりやらなかった仕事を回されると「できないからやらない」と宣言したり、自分から動かない。
- 「この先どういうキャリアを描こうか」という話題に対して、あまり関心を持たない。「今のままでいい」と思っている節がある。
向上心の欠如は、「なぜこの仕事をしているのか」「誰のために動いているのか」という原点を見失っていることの裏返しでもあります。
楽な仕事ばかり選ぶ・面倒な仕事は避ける
- 介助が体力的にきつい、記録が煩雑な、夜勤がある、というような仕事を配られると「自分休むので替わってください」「私はこっちでいいです」という態度。
- 自分の得意な業務(例えば利用者との会話が少ない、移動が少ない)だけをこなして、他の業務が滞ると「自分は手いっぱいです」と言って片付ける。
こうした行動が繰り返されると、現場の他の人の負担が増え、「なぜ自分ばかり…」という不満につながりやすいのです。
ミスや言い訳の繰り返し
- 同じミスを何度もしているのに、改善の動きが見られない。
- ミスを指摘されると「でもあの利用者さんがこう言ったから」「あの人がこうだったから」などと言い訳をする。
- 自分で「どうすれば良かったか」を振り返る姿勢が薄く、「次から気をつけます」で終わってしまう。
このような姿勢は、利用者の安全やサービスの質に直結するため、放置すれば施設運営自体にもリスクが生じます。例えば、遅刻・無断欠勤・サービス提供ミスなど、改善の見込みがない職員は最終的に解雇対象になる可能性もあります。
頻繁な休憩・勤務中の離席
- 業務時間中に私的な電話やネットをしていたり、タバコ休憩などで頻繁に席を外したりする。
- 「少し疲れたのでいいですか」「誰か代わってください」と言って、自分は介助から抜ける頻度が高い。
こうした行動があると、他の職員が代替で動くことになり、勤務分担がアンバランスになります。
また、利用者から見ても「この人は本気でやっているのか?」と疑問を持たれる原因になります。
なぜ「動かない職員」が出てしまうのか?背景を探る
ここまで「動かない職員」の特徴を整理しましたが、次はその根っこにある背景や理由を探ります。
個人を“悪”として片付けてしまうのではなく、なぜそのような状態になってしまったかを理解しておくことで、あなた自身の対応も、職場としての改善も行いやすくなります。
経験からの“勘違い”・固定観念
- 過去に「このレベルで十分だ」と感じた経験があり、それが“基準”になってしまっている。
- 「昔はこうだった」「この程度でいい」と、環境変化やサービスの質向上に対して柔軟に対応しようとしない。
このような思い込みがあると、「今の働き方で十分だ」「これ以上は求められていない」と自らハードルを下げ、結果として動かない・向上しない状態になってしまいます。
『期待されていない』と感じている
- 自分の役割・貢献が認められていないと感じている。
- 上司・同僚・経営側から「お前に期待してる」というメッセージが届いていない、あるいは届いていたとしても自分はそれを受け取れていない。
このような「自分はこの職場で貢献できていない」「自分を必要としてくれていない」と感じると、モチベーションが低下し、仕事に対する取り組み方がゆるくなることがあります。
働く意味・やりがいを見いだせない
- 「なんで自分はこの仕事をしているのか」「この施設・この利用者とどう向き合うのか」といった問いに対する自分なりの答えがない。
- 業務がルーティン化してしまい、「毎日同じことの繰り返し」「それでも給料は変わらない」という感覚が強い。
こうした「モチベーションの空白」「やりがいを感じない状態」は、身体は動いても心が動いていない状態=“動かない”ように見える職員を生みやすいのです。
私生活・ライフスタイル優先の思考
- プライベートを重視し、「仕事は最低限でいい」「定時間で終わればいい」という意識が強い。
- 介護の仕事の持つ責任の重さ・人手不足・残業・夜勤などを負担に感じ、その反動として「私生活優先」に傾く。
このような態度が習慣化すると、勤務態度・業務遂行に影響が出てしまいます。
以上のような背景が絡み合って、「動かない職員」が生まれ、そしてそのまま放置されることで職場の“負のサイクル”が回ってしまうのです。
“動かない職員”がもたらす職場への影響
この章では、具体的にどんな悪影響があなた自身に、そして職場全体に、さらには利用者さんにまで及んでいるかを整理します。
問題を放置するリスクを知ることで、「このまま我慢していていいのか/対策すべきか」の判断材料になります。
あなた自身への影響
- いつも自分が「動いている側」「助ける側」になってしまうことで、疲労・ストレスが蓄積する。
- 「他の人が働かない分、自分が埋めなきゃ」という責任感・焦りが生まれ、自分のパフォーマンスが落ちる。
- 仕事に対するモチベーションが徐々に下がり、「このままでいいのか」という不安が増す。
- プライベートの時間にも影響が出ることがあり、オン・オフの切り替えがうまくいかなくなったり、心身の疲労感が常時残ったりする。
職場・チームへの影響
- 負担の偏りが出ることで職員間の不公平感・不満が生じ、離職率が上がる。実際、人間関係の不満は介護職の離職理由で2割以上を占めています。
- チームワークが崩れ、「誰がどの仕事をするか」「どこまで進んでいるか」が見えづらくなり、業務ミス・伝達漏れが起きやすくなる。
- 業務の質低下、サービス提供のスピード低下、利用者さんやご家族からのクレーム増加につながる。
- 職場の雰囲気が重くなり、新たに入職した職員が「なんか働きづらい」と離れていくことも。
利用者・ご家族への影響
- ケアの遅れや質の低下につながることで、利用者さんが不安を感じたり信頼を失ったりする。
- 「あの人いつも動いていないな」「頼める人が固定されてるな」という印象を利用者さんが抱えると、サービス利用自体に不安が出る。
- ミスや不注意が重大な事故につながる可能性もある。特に介護現場では身体介助・転倒予防・認知症ケアなど、職員の動きや気付きが安全に直結します。
このように、「動かない職員」がいるということは“ちょっとした迷惑”を超えて、重大な構造的な問題になり得るのです。
あなたができる対処法―現場での“動けない人”との関わり方
では、あなた自身が“動かない職員”に対してどう動くか、そして自分の働き方を守るための具体的な方法も含めて解説します。
すべてを一度に実行する必要はありません。
少しずつ、自分にできることから進めていきましょう。
上司・管理者に相談する
まずは「自分ひとりで抱え込まない」ことが重要です。
「私だけこういう負担になっていて…」「あの人があまり動いてくれなくて…」という状況を、信頼できる上司や管理者に共有しましょう。
ポイント:
- 具体的な事実(何をいつ誰がして/しなかったか)を整理して伝える。
- 感情的にならず、「チーム全体の負担になっている」「利用者サービスに影響がある」という視点で伝えると、話が進みやすいです。
- 相談=愚痴ではなく、改善を意図しているという姿勢を示す。
上司と共有することで、配置や役割分担の見直し、研修・フォロー体制の強化など、組織側の対応が期待できます。
自分の仕事に集中する・影響を最小限にする
「あの人が動かないから…」と他人に引きずられて、自分の仕事まで影響を受けてしまったら意味がありません。
以下のような意識転換が役立ちます。
- 自分の役割・責任を明確にする。自分が「これだけはやる」という最低ラインを守る。
- 動かない職員を“変えよう”とはせず、「私がどう動くか」にフォーカスする。
- 休憩・オンオフの切り替えを意識して、自分の心身を守る。特に介護職は疲労・ストレスが溜まりやすいので、自己管理が大切です。
- 「あの人が動かない分、自分が動かなきゃ」という考え方を、「この状況だからこそ自分の強みを活かそう」「チームに貢献できる自分にフォーカスしよう」という方向に切り替える。
良好なコミュニケーションを心がける
動かない職員とのコミュニケーションにおいて、いきなり「どうして動かないんですか」「さぼってるんですか」と問い詰めるのではなく、関係を壊さずに動きやすくする工夫が効果的です。
- 相手の発言・立場をまず「そういう状況なんですね」と肯定してあげる。防御的になっている人ほど、自分の立場を守ろうとします。
- 負荷が偏っていること、チームとしてどうしたらいいか、自分の意見を「私はこう思っているんですが、〇〇さんはどう感じていますか?」という問いかけで共有する。
- 「〇〇さんがこう動いてくれたら、私もこの利用者さんにこう対応できます」というポジティブな提案型にする。
- 自分から笑顔・挨拶・声かけの頻度を上げておくと、雰囲気が変わりやすいです。単純ですが、“関わる人が変わる”ことで場が少しずつ動き始めます。
自分の心身を大切にする
この仕事を続けていくうえで、あなた自身の体・心を守ることが先決です。
- 「自分はこのままでいいんだろうか」「この職場で成長できているだろうか」という不安を抱えていたら、紙に「5年後、自分はどうありたいか」を書いてみるのも手です。そうすることで、“動けない人”に振り回されている状態から、“自分が動く”状態に切り替わります。方法です。
- 疲労を感じたら早めに休めるように、代替要員・シフト調整の相談をしておきましょう。
- 休日・オフ時間をしっかり確保し、仕事のことからいったん離れる時間を作る。
- ストレスを感じていると自覚したら、早めに相談窓口やメンタルヘルス支援を利用する。
それでも改善できなければ——“転職”を考えるという選択肢
ここまで、現場であなたができる対応策を見てきました。
ですが、「改善しない」「同じ状況が続く」「自分だけが頑張っている」という状態が常態化している場合、転職を真剣に検討すべきタイミングが来ている可能性があります。
あなたのキャリア・心身・働き方を守るためにも、「転職」という選択肢を否定せずに持っておくことが大切です。
転職を検討すべき兆候
以下のうち、ひとつでも当てはまるなら「今の職場・環境を見直すべきかも」と考えてみてください。
- あなたの負担が明らかに増えていて、上司・管理職に相談しても具体的な改善がなされない。
- 職場の雰囲気が明らかに悪化しており、あなた自身が“逃げ場”を感じられない。
- 利用者さんやご家族からのクレームが増えていたり、サービスの質低下を自分でも察知していたりする。
- 動かない職員だけでなく、複数名が同様の態度を取り、施設全体の構造問題になっている。
- 自分はこのままで成長できるのか、キャリアを描けるのかという見通しが描けない。
- ストレス・疲労・心身の不調(睡眠不足・職場の夢を見る・イライラが止まらないなど)が続いている。
こうした状態があるなら、「ここで頑張り続ける」ことが最善とは限りません。
むしろ、次の働き方・環境を探すことで、あなた自身が“動きやすい”状況に身を置くことが、長い目で見て大切です。
転職を選ぶメリット
- 新しい職場では、仕事に対する価値観・働き方・チーム体制が異なり、「動かない職員」問題が少ない・改善している可能性が高い。
- あなた自身が「自分はこういう環境で働きたい」「こういうチームで動きたい」と明確に描けていれば、転職を機にその理想に近づける。
- 転職活動を通じて、自分のキャリア・強み・価値を再確認できる。今後の働き方を自分で主体的に選ぶ意識が強まる。
- 転職によって給与や待遇、働きやすさ・研修制度・チーム構成などが改善されるケースもある。あなた自身が「もう少しラクに・でも誇りを持って働ける」環境をつくるチャンスです。
転職を選ぶ際の注意点
ただし、転職=すべて良くなる、というわけではありません。次の点には注意が必要です。
- 転職先の現場を事前にできるだけ調べること。動かない職員だけでなく、組織文化・上司の姿勢・教育制度などを確認しましょう。
- 転職理由を「この職員が動かないから」というだけにしないこと。あなた自身のキャリア・希望・働き方を整理して、「~だから次はこうしたい」という説明ができると、採用担当にも好印象です。
- あなた自身が「動ける人」であること、動きたいと思っていることを表明できるように準備しておく。転職先でも“期待される人材”になれるよう意識を持つこと。
- 転職活動と現職の両立が難しい場合もあります。体調・心の余裕を見ながら、無理のないスケジュールで進めましょう。
- 転職先で「ここもまた同じ構造だった」ということにならないよう、面接時や説明会でチーム構成・離職率・研修制度・職場風土などを丁寧に確認することをおすすめします。
あなたに合った“動きやすい職場”を選ぶためのチェックポイント
転職を前提に考えるなら、「動かない職員」に悩まない・悩みにくい職場を選びたいところです。
以下、チェックしておきたいポイントをリストアップします。
- 離職率がどれくらいか(特に中堅職員・新人職員の定着率)
- チーム内での役割分担が明確か。業務マニュアル・申し送り・記録・役割分担が整備されているか
- 管理者・施設長・リーダーなど職場を引っ張る人材がどれだけ機能しているか。上からの支援があるかどうか
- 教育・研修制度が充実しているか(新人研修・中堅フォロー・キャリアアップ支援)
- 働き方・シフト・休憩・残業などの制度が整っていて、私生活を守れる環境か
- 職場の雰囲気・価値観が「チームで助け合う」「改善を続ける」という方向か、あるいは「やればやっただけ」という個人任せか
- 面接・見学段階で「困っている職員」「負担が偏っている」「相談できる上司が不在」という雰囲気がないかを観察する
これらを自分なりに“合格ライン”として持っておくと、転職後に「また同じ悩み」になる可能性を下げられます。
転職エージェント登録を活用しよう
ここまで、現場で「動かない職員」とどう向き合うか、改善できないなら転職も選択肢だという話をしてきました。
最後に、あなたが「動く・環境を変える・次に進む」ための具体的なステップとして、転職エージェントの活用をおすすめします。
なぜ転職エージェントを使うべきか
- あなたの希望(働き方・シフト・チーム・施設規模・キャリア)を整理し、条件に合った求人を紹介してくれる。
- 面接・見学の調整・条件交渉・年収交渉など、あなた一人ではやりづらい部分をサポートしてくれる。
- 非公開求人や条件の良い求人を持っていることが多く、「次の職場環境」の選択肢が広がる。
- 転職活動に不慣れでもプロのアドバイザーがつくことで、安心して動ける。
登録・活用のポイント
- 「今すぐ辞めたい」わけでなくても、情報収集のために登録しておく。心に余裕が生まれ、選択肢を持っていることで現職での働き方も変わってきます。
- 自分の希望を明確に伝える(「動かない職員が少ない職場」「教育制度が整っている職場」「チームワーク重視」など)ことで、マッチ度の高い求人を紹介してもらえやすい。
- 面談で「この施設ではどんなチーム体制ですか?」「離職率はどれくらいですか?」「教育・研修制度はありますか?」と具体的に聞く。
- 転職後もサポートしてもらえるエージェントを選ぶ。入職前だけでなく、入職後フォローがあると安心です。
今、あなたにおすすめしたいステップ
- 現職をもう一度冷静に振り返る。「動かない職員」の存在・その影響・自分の負担がどうか。
- 転職エージェントに無料登録し、自分の希望条件を整理する。
- 面談またはオンライン相談で、「働きやすい職場とは何か」「自分はどう働きたいか」を明らかにする。
- 複数の施設(求人)を比較検討し、職場見学や説明会に足を運ぶ。可能なら現場の雰囲気・働いている人の様子を見る。
- 内定・入職後も、「動かない職員」問題が起きていないか・チームワークが取れているかを自分の感覚でチェックし、必要なら再び転職も視野に入れておく。
介護求人ラボ(株式会社ファミリーサポート)

❶ 保育・介護・歯科に特化した転職エージェント!!✨
❷ 厚生労働省が定める医療・介護・保育分野の適合紹介事業者に認定✨
❸ サービスエリアが全国に展開中✨
介護求人ラボは介護職の利用者数が多く、施設の担当者と様々な交渉をしてくれる事が魅力的です。
優先順位の高いエージェントと言えますので、登録しておく事をオススメします!
\無料登録は下記公式サイトから/
※登録後も費用は一切かかりません
リニューケア(株式会社renew career)

❶ 関西に特化した地域密着型の転職支援サービス
❷ リニューケア独自の情報網で求人情報・内部事情・転職動向を知る事が可能!
❸ 業界5年以上のコンサルタントが在籍
❹ 非公開求人も多数ある為、それぞれに合った求人を紹介して頂けます!!
リニューケアは求職者様を第一に考え、求職者様の「大切な家族」「大切な時間」「大切な生活」を最優先し、求人の提案・施設への交渉もして頂けます。
さらに、業界5年以上のコンサルタントが在籍しており、安心してご利用頂けます。
求人サイトや転職エージェントは複数登録が一般的なので、リニューケアにも登録して転職の幅を広げましょう!!
\無料登録は公式サイトから/
※登録後も費用は一切かかりません!
レバウェル介護(旧きらケア/レバレジーズ株式会社)
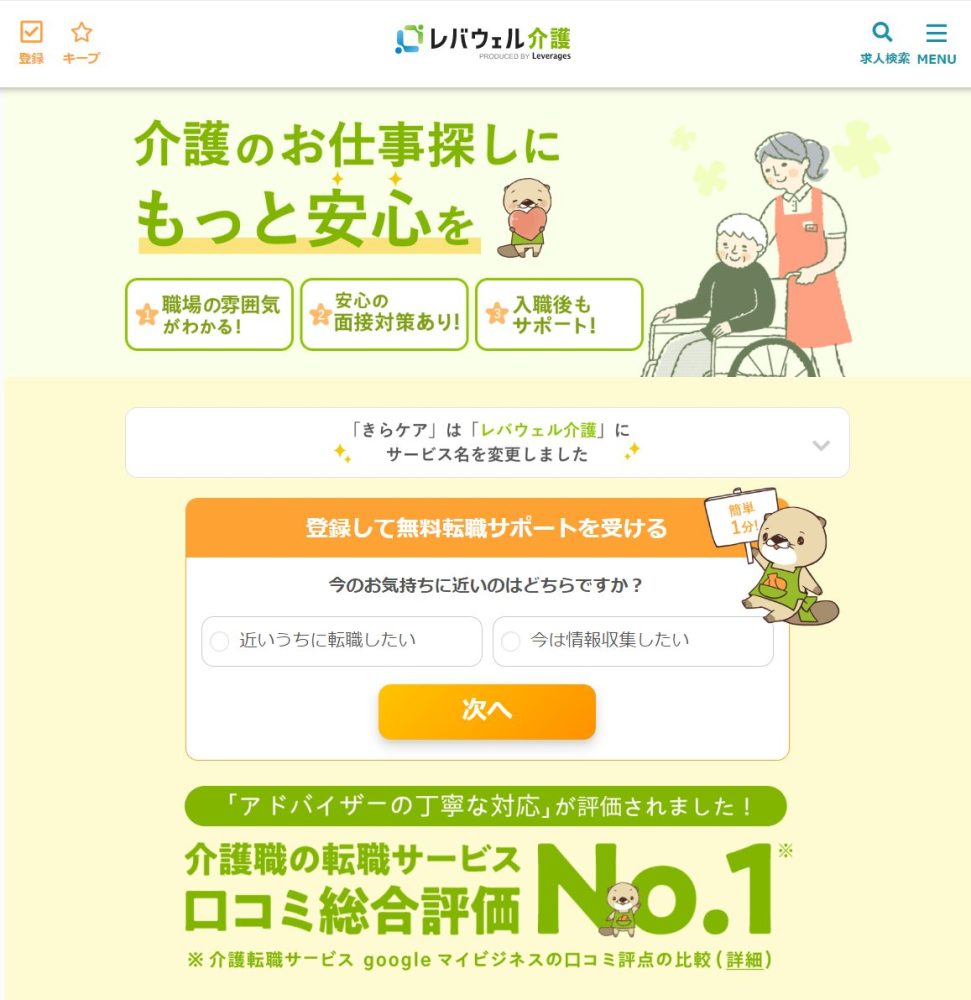
❶ 医療・介護系に特化したレバレジーズのサービスだからこその『非公開求人』多数!!約20,000件の公開求人もございます!
❷「無資格」「未経験」の方もサポート!
❸『給料前払いサービス』有り!お給料を、給料日よりも前に好きな時に引き出すことができるサービスがございます!
❹時給1700円の『高時給求人』を保有!
❺各地域ごとに専任のコンサルタントがいることで『地域密着型』のご提案が可能に!→実際に施設に足を運び、電話だけでは得られない職場の状況を踏まえたご提案をしています
全国対応しており、地域ごとに高時給求人を持たれています。
無資格未経験の方のサポートも充実してますので、介護業界にチャレンジしたい方は必見の派遣会社です!
\無料登録は公式サイトから/
※登録後も費用は一切かかりません
まとめ:あなたの“動き”が職場も未来も変える
ここまで、「動かない・モンスター化してしまった介護職員」と、あなたがどう向き合うか、そして環境を変えていくためのステップをご説明しました。
最後にポイントを振り返ります。
- 「動かない職員」がいると、あなたや職場・利用者さんに多大な負担・影響がある。
- ただ“個人の怠惰”と片付けず、背景・構造・環境も理解することで、対処が現実的になる。
- あなた自身ができること──上司に相談、コミュニケーション、自分の仕事に集中、心身ケア──を積み重ねることが重要。
- それでも改善が見られない/環境が変わらない場合は、転職という選択肢を持つことを強くおすすめする。
- 転職を成功させるためには、働きやすい職場のチェックポイントを押さえ、転職エージェントを上手に活用することがカギ。
- あなたのキャリア・働き方・人生を大切にするなら、「ここで我慢する」よりも「次を選ぶ」ことで、より安心して動ける職場にたどり着けます。
あなたが今、現場で感じている「なんであの人が…」「自分ばかり…」「このままでいいのか…」というモヤモヤは、あなたの働く価値・チームとしての価値・そして利用者さんに対する価値を大切にしている証です。
その価値を守るために、まずは自分の環境を整えましょう。そして、もし今の環境でそれが難しいと感じるなら、次の職場を探すことも「逃げ」ではなく「選択」です。
転職エージェント登録は、今この瞬間から始められます。
情報収集だけでも十分意味があります。あなた自身が「安心して動ける職場」を手に入れて、一歩前へ進んでください。あなたの次のステージを、応援しています。
最後まで読んで、頂きありがとうございました。